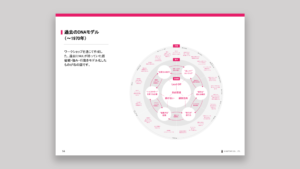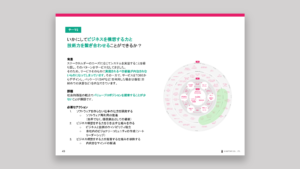事業内容の変化に伴い、徐々に存在意義を喪失
2017年ごろの役員合宿の際に「自社の存在意義に関する認識が不明確なのでは?」という意見が出て、社内で議論してきました。日本ユニシスはもともと米国ユニシス製品の販売・保守拠点として国内企業と合弁で法人を設立し、事業をスタートしましたが、事業環境の変化に伴い、資本関係を解消し、事業内容を大きくサービス中心に再構築してきた歴史があります。この先、主体性をもって将来の展望を描いていくためには、社名変更前にこの問題を整理しておく必要があると判断し、2020年に存在意義を探索するプロジェクトを立ち上げることにしました(永井)。
国内の熱心なユーザーや、米東海岸の企業や大学関係者と接していると、ユニシスは世界初の大型汎用コンピュータの誕生にかかわり、それを発展させてきた企業として認識されています。ところが、社内ではそのように認識されておらず、外からの評価と内での評価の食い違いを感じていました。そもそも、自社の成り立ちを知らない社員も多く、そうしたことも存在意義の認識が喪われてしまうことにつながってしまったのかもしれません(羽田)
未来年表を描いてチーム共有ビジョンを作成
問題解決のために、どこから手をつけていいのか迷っていたところ、知人に強くすすめられたのがBIOTOPEの佐宗邦威さん。そこでホームページからアポイントを取り付け、BIOTOPEのオフィスへキックオフミーティングのために訪問したところ、1時間の予定だった打ち合わせが約4時間にも及んだのは衝撃的でした。わたしはB2Bサービスというのは、患者と医者の関係にどこか似ていると感じていて、患者の症状をきちんと把握しようとする医者は正しい処方をすると思っています。だから、我々が相談に至った背景を深く理解するために、長い時間をかけるBIOTOPEは信頼できるパートナーだと確信しました(永井)。
当日はチーム共有ビジョン作成のために、参加したコアメンバーがプロジェクト達成後に実現したい未来を描くワークを行いましたが、よくあるコンサルのやり方と違い、いろんな状況に合わせて、自分たちの手でつくり上げていく印象を受けました。コロナ禍だったこともあり、結果的に対面でのミーティングはこの1回だけになってしまいましたが、DIYでリノベしたようなオフィス空間からも、型にはまらないBIOTOPEのクリエイティビティが伝わってくるようでした(羽田)。
存在意義を見つめ直す部署横断のワークショップ
本番のワークショップに向けた準備として、佐宗さんから歴史年表の整理と過去の成功事例を関係者にインタビューするという事前課題があったことから、BIOTOPE側が我々の説明をヒアリングして治療仮説を立てたと理解しました。患者の症状の詳細を確認したうえで、この処方箋がいいというシナリオを用意したのであれば、時間的な制約はあるにせよ、それに則ってやってみようというのがプロジェクトメンバーの総意でした(永井)。
ワークショップの1回目では、顧客主導の業務のなかで“自分”が見えなくなった、あるいは提供サービスが多様化してしまったために企業としての共通認識がもてない、といった課題に対して、事前に準備した資料を発表後、参加メンバーたちがそれについて話し合いました。歴史や価値観、自分たちの強みなどの洗い出す過程で印象的だったのが、普通の質疑応答では表層的な答えになってしまいそうなところを、BIOTOPEでは内面に切り込んでくる質問をして、思考で判断するのではなく深く思いを巡らせないと答えられないような掘り下げ方をすること。途中から、メンバーそれぞれが本当に思っていることを語り出したのには少し驚きました(羽田)。
若手を加えたメンバーで課題に対する意識を再確認
1回目のワークショップ後に佐宗さんから参加者をもっと多様化したいという要請があり、若手2名を加えました。実は我々も最初からそういう視点で老若男女、立場の違うメンバーを選んだつもりでしたが、出てくる課題が似通っていたため、少し場を掻き回すような社員を追加しました。ただ、それでも出てくる意見は一緒。その後ふたりのインタビューを行いましたが、意図しなくてもDNAが共有されていることをあらためて感じました(永井)。
2回目のワークショップでは、前回つくった自分たちの価値観、強み、行動を円状に配置した”過去”と”現在”のDNAモデルを踏まえて、将来のあるべき姿を話し合いました。「日本ユニシスのDNAをつくるとしたら特に重要なことは何だろう?」というテーマで、セールスサイクル、イノベーションサイクルに分けて議論後、それを統合しましたが、いままでぼんやりと感じていたことを可視化できたのが収穫でした。それを見て気づいたのがオープンネットワーク時代に突入した1996年あたりを境に、それ以前を経験した社員と経験していない社員では考えに少し隔たりがあったこと。メンバーをちらしたようでいて、すでにそれ以降の世代が社内の中心になっていることが、似た意見が多くなってしまった原因だと気づきました(羽田)。
これまでの議論をストーリーとして統合
その後、存在意義を言語化するために、コアメンバーでこれまでのインタビューやワークショップで出てきたメッセージを集約していきましたが、自分たちの存在をどう説明するかは以前からわたしなりにずっと考えてきたこと。デジタルという言葉は不可欠として、製品を売るわけでもコンサルを行うわけでもない、自社の立場を考えたときに業態としていちばん近いと感じたのが、新しい“しくみ”をつくる商社でした。そこで出てきたのが、デジタルに根ざしたところで、これまでの世の中にないしくみをつくる「デジタル商社」という言葉。これを最終形にするには、もう少しブラッシュアップが必要だと思っています(永井)。
ワークショップの合間にも社内向けSNSで活発に議論を続けていましたが、驚いたのはDNAモデルの更新を行う場面で、以前は過去の話題に反応しなかったメンバーが、核となる価値観や強みに想定外の言葉を選んだこと。解釈によって誤解を生みそうなので、大っぴらな開示は控えていますが、歴史年表でそこまで動くとは思いませんでした。3回目のワークショップでは、前もって定めていたこれからの行動原則をもとに、それに必要なアクションプランを話し合って終了。社名変更のタイミングだったからかもしれませんが、みんなの変わろうという意識が強かったのが印象的で、いまもそれについての議論は続いています(羽田)。